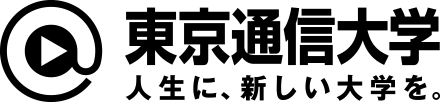専門教育科目:人間福祉学部
人間福祉学科
包括的支援体制の基礎
専門教育科目:人間福祉学部
人間福祉学科
包括的支援体制の基礎
人間福祉学部の専門教育科目は、6つの分野を総合的に学びます。医学、心理学、社会保障などを学ぶ「ソーシャルワーク」、様々な支援の取り組みや体制について学ぶ「包括的支援体制の基礎」、人間の生活を支える福祉を体系的に学ぶ「社会福祉」と「精神保健福祉」、人間の個別性と多様性を理解するための「総合人間」、実地の演習を通じて各分野に対する実践力を身につける「フィールドスタディ」。これらの科目を学ぶことで、従来の専門的福祉教育に加え、人間社会に対する広範な知識を身につけます。
※3年次編入学の方へ
厚生労働省による社会福祉・精神保健福祉養成課程のカリキュラム見直しにより、一部科目の科目名、単位数、標準履修年次などが異なります。
3年次編入学の指定科目名称は「国家資格取得に関する案内」で確認ください。
- <授業形態について>
-
- メディア ・・・ PCやスマートフォン等で受講できるメディア授業
専門教育科目:包括的支援体制の基礎
※科目に関する情報は変更になる可能性があります。
| 科目名 | 保健福祉学総論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
地域包括ケアを推進するためには、保健福祉の歴史や制度の流れ、現状と課題を知ることは重要である。本講義では保健・福祉の歴史を概観し、日本で子ども、女性、高齢者、障害者等が抱える福祉的な時事問題を取り上げ、対策を検討する。また、人間の成長発達段階を学び、発達段階ごとの現状と課題、ライフサイクルに合わせた支援策を学ぶ。 1)保健と福祉を学んでいく。 2)日本の社会保障の概論を学んでいく。 3)ライフサイクル別の福祉対策を学んでいく。 |
||
| 科目名 | 介護の基本 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
超高齢社会を迎えたわが国においては、医療ニーズ・介護ニーズの多様化・重度化にともない、地域における総合的な福祉サービスの提供とともに、包括的相談援助ができる人材の育成が求められている。介護の基本では、次の内容を取り上げ、学習する。 1)介護の歴史的変遷と介護証が誕生した社会的背景について学ぶ。 2)介護福祉の基本理念と介護福祉の倫理について学ぶ。 3)介護の対象と介護を提供する場について学ぶ。 4)介護を提供する場と利用者を取り巻く関係職種と連携の必要性について学ぶ。 5)介護における安全の確保と介護従事者の安全について学ぶ。 |
||
| 科目名 | 福祉施設・病院経営論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
福祉施設全般意義と諸課題、福祉施設における事業会計課題について理解を深める。具体的には、福祉施設の運営・経営について、現場に即した事例を示しながら講義していく。今後福祉施設に就職する時に、相応しい施設を選択できることを最終目的とする。福祉施設がどのような枠組みか理念は何か、どのような人材と財源等で、運営されているのかを学んでいく。 1)法人経営の理論を学び、実際の経営手法を理解する。 2)福祉施設・事業の経営組織のあり方を知る。 3)福祉施設・事業の人事・財務・開発等を学び、実際のサービス展開を知る。 |
||
| 科目名 | 共生社会論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
共生社会は、民族・文化・立場等の異なる人々がお互いを認め合い、ともに生きていこうとする社会の実現をめざしている。さまざまな視点から共生社会を論じられるが、ここでは、主として社会福祉学、インクルーシブ教育システム、コミュニケーション教育の立場から講述する。共生社会を阻むものを壁と考え、「制度の壁、心の壁、言葉の壁」等を含めた「社会的障壁」の視点から考えていく。 1)共生社会に関連する基本的理念を考える。 2)共生社会の理論的基盤を考える。 3)制度の壁を考える。 4)心の壁を考える。 5)言葉の壁:コミュニケーションの問題から第2言語としての日本語教育と多文化共生の関連を考える。 6)社会的障壁 |
||
| 科目名 | 地域包括支援 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
地域包括支援は、尊厳ある生活の実現に向け、地域社会を基盤とした地域包括ケアシステムを構築するために、医療・保健・福祉サービスと地域住民の多様な支援活動を横断的に調整し、支援を必要とする人々に提供することである。 地域包括ケアシステムの構成要素として住まい、生活支援、予防、介護、医療などがある。本授業では、「住まい」と「予防、介護、医療」に焦点をあてる。具体的には、 1)個人のライフステージに応じて豊かに暮らし続けるために地域にある多様な「住まい」を理解する。 2)地域包括ケアシステム展開の経緯を踏まえ、その人らしい「住まい方」を実現するための専門職との連携やコーディネイトについて知る。 3)予防、介護、医療の観点から高齢者の健康や食に関する支援における多職種連携とその事例を知る。 |
||
| 科目名 | 障害者スポーツ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
1964年に東京で第1回パラリンピックが開催されてから60年近くがたち、障害者スポーツは日本のみならず世界各地で発展と普及を続けている。本科目では、障害者スポーツの歴史、障害者の社会参画、競技、自己実現、障害者スポーツが社会に与える影響などの現状を学び、その在り方を考えていく。 1)障害者スポーツの発祥、発展の歴史 2)障害者スポーツの担い手 3)障害者スポーツの種目 4)パラリンピック・ブレイン 5)パラリンピックとスペシャルオリンピック |
||
| 科目名 | 福祉心理学 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
福祉心理学は、福祉問題に関する心理学的研究であり、社会福祉研究の立場からも、心理学研究の立場からも、その研究の発展が期待される学際的研究領域である。本授業において福祉の充実発展のために、 1)福祉の対象となる人々の心理を十分に把握する。 2)福祉活動に携わる人の心理的問題を知る。 3)福祉的対応を必要とする人たちの家族の心理的問題を知る。 4)福祉的対応を必要とする人たちとその家族を知る。 5)福祉業務に従事する人たちの人間関係に関する心理的問題を知る。 |
||
| 科目名 | 福祉と特別ニーズ教育 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
障害者を巡る状況が、近年、大きく変わり始めている。その背景には国連の障害者権利条約、障害者差別解消法が大きくかかわっている。障害者に必要な支援は、福祉、教育、医療、労働、司法等、かなり広範囲にわたっている。障害者差別解消法では、差別の禁止と合理的配慮の提供が明記され、インクルーシブな教育や社会に向けて大きく舵を切っている。 本授業において福祉と教育の接続が重要であるとの認識に立ち、 1)特別ニーズ教育とは何かを知る。 2)これがインクルーシブな教育や社会にどのように貢献しているかを学ぶ。 |
||
| 科目名 | 生と死の福祉論A | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 3・4学期 |
| 授業の概要 |
ソーシャルワーカーは、人の生きる世界に入り、その人の生きる世界を共にしながら、それら生老病死の苦しみからの解放と、一人一人が生きたいように生きることができる人生の創造を支える専門職である。したがって、この科目は、人間の生老病死に関心をもち、それを社会福祉の課題から捉えるとともに、自らの価値を見つめ、それをソーシャルワーカーの価値、倫理の学びにつなげる。 1)生老病死(生まれること、老いること、病気をすること、死ぬこと)は、人間が生きる上で避けられないライフイベンツであることを理解することができる。 2)社会問題を生み出す構造について理解することができる。 3)社会問題による人々の生老病死について関心を持ち理解することができる。 |
||
| 科目名 | 生と死の福祉論B | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 3・4学期 |
| 授業の概要 |
生と死の福祉論Aに引き続き、「生老病死」について身近なテーマについてさらに関心を深める。 1)ソーシャルワークの価値及び倫理の学びの前提となる、人間の生老病死に対する自らの関心、態度について省察し、他者理解、対象者理解につなげることができる。 2)人間の生老病死に関し、積極的に関心を持ち、関係する情報について主体的に探究することができる。 3)人間の生老病死に関し、他者の意見を聴きながら、自らの意見を醸成させ、それを表現することができる。 |
||
| 科目名 | サルコペニア・フレイル予防論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
生活機能障害を招き、健康長寿の妨げになるものとしてサルコペニアやフレイルが注目されている。その重要性を理解し、病態、疫学、介入法などについてエビデンスを構築するための基礎知識と技能を習得する。 1)サルコペニア、ロコモティブシンドローム、フレイル、オーラルフレイルなどの意義・診断・治療を理解する。 2)サルコペニア・フレイルの予防戦略について栄養、運動、薬物の観点から学ぶ。 3)医療・福祉・地域などでのフレイル・サルコペニアの予防・介入についての取り組みを学ぶ。 |
||
| 科目名 | 地域居住と包括ケア | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
「エイジング・イン・プレイス」と言う概念が地域居住としてわが国でも定着してきた。住み慣れた地域で、その人らしく最後まで安心した生活を継続するには、ライフステージに応じて変化するその人その人の多様なニーズを把握し、地域にある医療・看護・介護・福祉などの専門的なケア・支援の関わりについて検討していくことが重要である。この授業では、地域包括ケアシステムにおいて、生活の基盤となる「住まい」とそこでの「住まい方」に着目し、生活を多様な形で継続していくためのケアのあり方について学ぶ。 1)地域包括ケアシステムにおける「すまいと住まい方」を知る。 2)地域包括ケアシステムにおける地域に住み続けることを知る。 3)地域包括ケアシステムにおける多職種連携を知る。 |
||
| 科目名 | 生活保護と行政 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
現代社会における生活保護制度の基本的事項を説明する。特に、講義では次のことについて考える。 1)生活保護制度がどのような構築されてきたのかについて学ぶ。 2)生活保護制度がどのようにして現場で運用されているのかについて学ぶ。 3)生活保護制度が生活困窮者にどのように影響を及ぼしているのか改めて考えていきたい。 |
||
| 科目名 | 災害福祉論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
災害が起きたことによって生じてくる生活課題への支援について総合的に学び、災害支援のあり方や防災・減災に向けて社会福祉学の視座から私たちは何ができるのかを考えていく。また、人や地域を支えていくことの意味を問い直していきながら、わが国で生活を送る上で見つめるべきことを探っていく。 |
||
| 科目名 | NPO概論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
特定非営利活動について、具体的な事例等を取り上げて学んでいくこととする。NPO活動に関する歴史であったり、法制度について確認していく。NPO法人の設立に関する各種手続きや運営方法についてもみていくこととする。また、実際の運営にあたっての現状と課題についても事例を基に検証していくこととする。 |
||
| 科目名 | 福祉産業マネジメント論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
少子高齢化が急進し、社会保障制度の改革が求められる中、福祉産業に対する社会的ニーズも年々多様化してきている。本講義では、介護ビジネス及び障害者就労ビジネスを取り上げる。 1)福祉産業界の特徴や特性、最近の業界動向を理解する。 2)社会福祉関連の問題や福祉ビジネスが直面する経営課題について学ぶ。 |
||
| 科目名 | 社会資源開発・共同体創造論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
医療保健福祉領域における社会資源の開発には様々なプロセスが生じる。そしてそのプロセスを踏む前には必ず問題・課題を抱えた「当事者の思い」が存在する。対人援助職に就く人にとって、この「当事者の思い」と向き合いつつ願いを叶える環境をどのように作り上げていくかは喫緊の、あるいは持続性を伴う活動であろう。 本科目はリカバリー理論に基づく資源開発の方法、co-production(共同創造・共同作業)の基礎から実践までを紹介する。世界基準の方法論の確認、社会資源の立ち上げから、運営方法、ネットワーク形成の実践的方法論の習得を目指す。 |
||
| 科目名 | スクールソーシャルワーク論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
今日におけるスクールソーシャルワーク(SSW)の必要性と意義を解説し、学校教育と社会の状況をふまえ、子どもや家庭、学校を支援するための方法を学ぶことを目的とする。 1)スクールソーシャルワークの必要性と意義を学ぶ。 2)子ども・家庭・学校の現代的状況を学ぶ。 3)学校教育の仕組み・法制度・文化の特徴と教育職・心理職など多職種連携による支援について学ぶ。 4)不登校・LGBTQ・発達障害などさまざま背景を有する子どもや家庭に関する社会資源について学ぶ。 |
||
| 科目名 | 医療ソーシャルワーク実践論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
医療保健分野のソーシャルワークについて実践の方法や考え方について学ぶ。事例や資料を教材として活用しながら、疾病や怪我をきっかけに起きる生活障害を理解し、また患者や家族の心理社会的側面に関心をよせるソーシャルワーカーの視点を身につけ、生活問題や福祉問題への介入の具体的方法など実践の力の習得を目指す。ソーシャルワークの介入は社会科学的な視点から提供されるものであり、正答は一つとは限らないことを理解しながら、基礎的な理解に裏付けられた介入の多様性を考える講義になる。メディア講義を中心に行い、小テストや単位認定試験では記述式の解答を求めることがある。 |
||
| 科目名 | 福祉のまちづくり論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 4年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
少子高齢社会となったわが国では、様々な人々のそれぞれのニーズに応じた誰にでも使いやすいデザイン、生活しやすい環境の整備の重要性が着目されている。物理的な環境としての住宅、施設といった多様な住まいを個別に「点」として整備するだけでなく、地域生活を継続するための交通手段や道路、公共施設など「線」をつなげて「面」として連続させていくことで総合的な環境整備が必要となってきている。特に、地域環境については、地域ごとの環境特性や自治体の制度整備状況も関係してくる。そのため地域、まちを総合的な視点で捉え、環境整備をしていくことが求められる。多様なニーズを持つ人々が共生できるまちづくりについて歴史的変遷を踏まえて学習する。 1)地域生活とまちづくりについて 2)まちづくりに必要な情報について 3)福祉のまちづくりと地域包括ケアシステムについて |
||