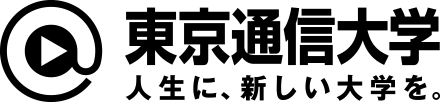教養教育科目:両学部・学科共通
自然科学
教養教育科目:両学部・学科共通
自然科学
現代社会の課題を広範囲にカバーする教養教育科目。
幅広い選択肢の中から、目的や興味に応じて選ぶことができます。
- <授業形態について>
-
- メディア ・・・ PCやスマートフォン等で受講できるメディア授業
教養教育科目:自然科学
※科目に関する情報は変更になる可能性があります。
自然科学
| 科目名 | 物理学概論Ⅰ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
理工系を専門とせずに自然科学について学ぶ学生のために、私たちの身近にある自然現象についてのいくつかの疑問について、できるだけ数式を使わないで考えることにより、自然現象を物理的に説明する方法について理解を深める。「なぜ」という疑問を持つことは、自然科学に限らず人文科学、社会科学の分野でも大切な姿勢であり、私たちが何気なく接している自然現象にも物理学の根幹に関わる多くの「なぜ」があることを学ぶ。本授業では力学を中心に以下の内容について学ぶ。 1)運動とニュートンの法則 2)エネルギーと熱 3)振動と波 4)電気と電気回路 |
||
| 科目名 | 物理学概論Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
理工系を専門とせずに自然科学について学ぶ学生のために、私たちの身近にある自然現象についてのいくつかの疑問について、できるだけ数式を使わないで考えることにより、自然現象を物理的に説明する方法について理解を深める。「なぜ」という疑問を持つことは、自然科学に限らず人文科学、社会科学の分野でも大切な姿勢であり、私たちが何気なく接している自然現象にも物理学の根幹に関わる多くの「なぜ」があることを学ぶ。本授業では電磁気を中心に以下の内容について学ぶ。 1)電気と磁気 2)光 3)電磁波 4)物理学の未解決問題 |
||
| 科目名 | 霊長類学入門 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 3・4学期 |
| 授業の概要 |
この授業では霊長類に対し生物学・生態学・心理学・神経科学・社会学等多様な視点から学問的アプローチを行う「霊長類学」について、その概要や発展の歴史、各学問領域における研究成果を通して、霊長類を含む生物の多様性や環境保護、持続可能な社会のあり方について考察していく。1)霊長類学の歴史2)霊長類の進化3)霊長類と自然4)霊長類としての人間 |
||
| 科目名 | 生活の化学 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
化学という学問の歴史や守備範囲の説明からはじめて、基本となる原子や分子を理解する。次に生活の中で最も使用頻度が高く種類の多い材料である、高分子を詳細に説明していく。まず、高分子とは、そしてどこで使われているか概要を示し、色々な高分子の合成法、特徴をそれぞれの高分子について理解した後、生活の中のいろいろな場面で使用される高分子について理解する。最後に高分子のリサイクルと環境への影響を理解する。 |
||
| 科目名 | 科学コミュニケーション論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
科学技術の発展と普及を支える要素の一つとして科学コミュニケーションがどのような役割を果たしてきたのかについて学ぶ。 1)科学コミュニケーションの発展の歴史について学ぶ。 2)現代社会における科学コミュニケーションの担い手や人材育成について学ぶ。 3)コミュニケーションのためのリテラシー獲得、場つくり、手法について学ぶ。 4)科学への市民参画について学ぶ。 5)科学技術政策との関係について学ぶ。 |
||
| 科目名 | 統計学入門 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
我々の生活では平均寿命、日経平均株価などたくさんの統計指標があふれている。 しかしながら、統計指標は必ずしもデータが持つ事実を正確に表していない場合があるため、これらの統計指標が表すこと、および表していない事は何かを読み解く力が必要になる。 この科目では、極力数式を用いずに統計指標の読み取り方や作り方、さらに実際のデータの統計処理を行う知識と技能の獲得を目指す。 1)身の回りの統計指標が持つ意味を説明できる。 2)身の回りでどのような統計学の知識が用いられているかを説明できる。 3)アンケートの結果に対して簡単な統計処理を行うことができる。 |
||
| 科目名 | 数学基礎Ⅰ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
東京通信大学での学びを進めるにあたって、統計学やデータ解析の学習などで数学を用いる機会がいろいろと生じる。 この科目では、数学の基本的な概念を学び、数学的な考え方を学ぶとともに、例題を通じて基本的な計算技能を身につけ、もって東京通信大学で学ぶために必要な数学の基礎力を養う。 具体的には、次の項目を学ぶ。 1)数と計算、等式・不等式・方程式などの概念と性質 2)図形の性質 3)関係と関数 |
||
| 科目名 | 数学基礎Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
東京通信大学での学びを進めるにあたって、統計学やデータ解析の学習などで数学を用いる機会がいろいろと生じる。 この科目では、数学の基本的な概念を学び、数学的な考え方を学ぶとともに、例題を通じて基本的な計算技能を身につけ、もって東京通信大学で学ぶために必要な数学の基礎力を養う。 具体的には、次の項目を学ぶ。 1)関数の性質と様々な関数、三角関数 2)場合の数と離散確率 3)極限、微分と積分の初歩 |
||
| 科目名 | 線形代数Ⅰ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
自然科学や工学の分野を学ぶにあたっては、基礎的な数学の知識を身につけておくことは重要であり、本学での学びを進めるに際にもそれらの知識が必要となる場合がある。本科目では、数学の中でも重要な分野の一つである線形代数について、その基礎として以下を学ぶ。 1) ベクトルの定義と計算 2) 行列の定義と計算 3) 一次変換 また講義の中では、例題を通じて具体的な問題を解くことにより、基本的な計算の技能も身につける。 |
||
| 科目名 | 線形代数Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
自然科学や工学の分野を学ぶにあたっては、基礎的な数学の知識を身につけておくことは重要であり、本学での学びを進めるに際にもそれらの知識が必要となる場合がある。本科目では、「線形代数Ⅰ」で学んだ行列の知識に基づいて、より発展的な内容を学ぶ。具体的には以下を学ぶ。 1) 連立一次方程式の解法 2) 行列式 3) 固有値・固有ベクトル 4) 行列の対角化 また講義の中では、例題を通じて具体的な問題を解くことにより、基本的な計算の技能も身につける。 |
||
| 科目名 | 微積分Ⅰ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
自然科学や工学に類する内容を学ぶにあたって、微分と積分の概念は必須の知識である。この科目においては、微分積分の知識を前提とはせず、数学の基本的な知識に基づいて微分の概念を理解し、実数の一変数関数の微分の計算ができる技能を身につける。 1)実数や数列、関数の定義を知る 2)様々な関数の性質と導関数の定義を知る 3)微分法の基本公式を知る 4)曲線の外形から平均値の定理を知る 5)平均値の定理と微分法の応用を知る |
||
| 科目名 | 微積分Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
この科目においては、「微積分Ⅰ」で学んだ微分の定義とその解法の知識に基づいて、逆演算としての積分の概念を理解し、実数の一変数関数の積分の計算ができる技能を身につける。また、さらに進んで微分積分の応用としての微分方程式を理解する。 1)不定積分の定義と様々な関数の積分の解法を知る 2)積分法の基本公式を知る 3)定積分や広義積分によって面積や曲線の長さが求められることを知る 4)数列の無限和としての級数の定義を知る 5)微分積分の応用としての微分方程式を知る |
||
| 科目名 | 食の安全学 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 3・4学期 |
| 授業の概要 |
食品の安全性について多様な観点から理解する。個々の食品の安全性を脅かす問題点を明らかにすることにより、健康を守る実際的な方策を立てることができるようになる力を養う。 1)食品の安全性の意義と、まつわる法規を理解する。 2)食品の腐敗・変敗や食中毒を理解し、食品の安全性を確保する手立てについて学ぶ。 3)環境汚染物質による食品汚染について理解する。 4)消費者が安全な食品を選択するための食の安全流通や表示、管理について学ぶ。 |
||