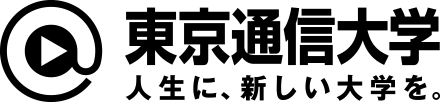教養教育科目:両学部・学科共通
社会科学
教養教育科目:両学部・学科共通
社会科学
現代社会の課題を広範囲にカバーする教養教育科目。
幅広い選択肢の中から、目的や興味に応じて選ぶことができます。
- <授業形態について>
-
- メディア ・・・ PCやスマートフォン等で受講できるメディア授業
教養教育科目:社会科学
※科目に関する情報は変更になる可能性があります。
社会科学
| 科目名 | 日本国憲法 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 2 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
憲法をなぜ学ぶかを考え、日本国憲法の基本的理念と体系を理解することにより、基本的人権を擁護し、社会に適用する教養を身につける。具体的な生活の場、社会において日本国憲法がどのように関係しているかを具体的に知る。 1)憲法の全体像、立憲主義、憲法の3原則を確認する。 2)平和主義と憲法9条、前文を確認する。 3)幸福追求権、プライバシー権、精神的自由、人身の自由について確認する。 4)経済的自由を確認する。 5)社会権、基本的自由権を確認する。 6)参政権、国民主権を確認する。 7)立法権、行政権、司法権を確認する。 8)地方自治を確認する。 |
||
| 科目名 | 心理学入門A | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
自己理解および他者理解を深めるための人間理解の基礎的な考え方を身につけるために、主に対人支援、性格、発達、社会に関する心理学的知見について理解し、私たちの心の働きを科学的に明らかにしようとする学問としての心理学の考え方を認識できるようになる。 1)心理学が「心と行動の科学」とされる理由を認識する。 2)心理に関する支援の範囲と種類を知る。 3)性格をとらえる枠組みを知る。 4)加齢に伴う心と行動の変化を知る。 5)他者・社会とのかかわりによる心理的影響を知る。 |
||
| 科目名 | 心理学入門B | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
日常生活場面での自己と他者の行動に関心を示し、人間理解の基礎的な考え方を身につけるために、主に知覚、認知、学習に関する心理学的知見について理解し、私たちの心の働きを科学的に明らかにしようとする学問としての心理学の考え方を認識できるようになる。 1)ものを見る、音を聴く仕組みを知る。 2)記憶のプロセス、問題解決の特徴を知る。 3)学習の種類とその応用を知る。 4)脳と心の関係、脳損傷と心の働きを知る。 5)心理学の研究方法、心理学の歴史と展望を認識する。 |
||
| 科目名 | 選択理論心理学概論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
選択理論心理学は、人がどのように現実を認知し、動機づけられ、行動するかを、脳を機能システムとみなして説明する理論である。人は自らの行動を選択していると考え、セルフ/モチベーションコントロール、マネジメントなど、広範な領域に適用可能である。概論では、脳の機能、人間関係や欲求充足等に関する知識を修得する。 1)選択理論心理学の歴史的な流れを概観し、効果的に身に着けるための手法について理解する。 2)脳の働きを理解し、選択理論心理学の用語を使って、人が行動を選択する仕組みを説明する。 3)実践的に使うために、自己制御、人間関係構築など、様々な状況における行動選択の基準を理解する。 |
||
| 科目名 | 医療社会学 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
医療社会学とはどのような学問であるのか、その基礎について解説するとともに、現代の医療をめぐるさまざまな問題について、具体的な事例を用いながら考察する。 1)医療社会学が誕生した背景や、その後の理論や学説の展開について学ぶ。 2)医療社会学の代表的な研究や関連研究について解説する。 3)現代の医療をめぐるさまざまな問題を取り上げ、どのような課題や議論を有しているのかを考察する。 |
||
| 科目名 | 相互扶助の経済と文化 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
現代社会における「交換」の形態は多様である。現代では財やサービスが一つの「商品」として、市場で交換されている。他方、市場原理から切り離された贈与交換も存在し、文化的要因に関連した相互扶助の機能を担っている。本講義では、理論と事例の双方から「交換」とは何かについて考えていく。 1)様々な交換論 2)フィジー社会における相互扶助の機能を担う「ケレケレ」という交換形態 3)日本社会の相互扶助に関する経済と文化の理解 |
||
| 科目名 | 経済人類学 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
現代の地域経済は、K.ポランニーが「自己調整的市場」と呼ぶ画一的システムに置換されつつあるが、地域に固有の伝統的価値は消失したわけではない。近代経済学の「経済人」に基づく分析は、特定の時代や社会の文脈から切り離して行われる。しかし経済人類学は、経済主体の実践を、「地域に固有な価値体系と分かち難く絡み合った市場」概念を通して理解することを目指す。本講義では、経済人類学という視座を学ぶことで、より深い経済学の地平を拓きたい。 1)市場の暴力性 2)地域に固有な価値体系 3)市場概念の再検討 |
||
| 科目名 | アジア経済論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
年季契約労働者制度により、多くのインド人が大英帝国の植民地プランテーションに渡った。契約満了後も現地に残る選択をした彼らの子孫が、今日、「インド人ディアスポラ」として世界中に居住する。本講義では、アジア地域、とりわけインドを取り上げる。そして、世界の各地域に居住するインド人ディアスポラが現在置かれている社会経済的状況を分析し、彼らがインド本国と新たな経済的社会的諸関係を築きつつある昨今の情勢を理解する。 1)年季契約労働者制度 2)ディアスポラ 3)グローバル化とアジア経済 |
||
| 科目名 | 平和学 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
日常においてますます国際社会との関わりが深まりつつある現代にあって、「平和学」につき、政治(含む国際法)、経済(含む情報IT)、社会(含む人間福祉)の多面的な視座から理解を深める。本講義では具体的な実務経験から考えた事柄を中心に授業を展開する。世界情勢と日常を身近に例にとりつつ、これからますます重要になっていくまだ新しい学問である「平和学」の基礎的視点を養う。 |
||
| 科目名 | 社会学概論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
社会学の代表的な古典について学ぶことによって、社会学的思考の成り立ちを理解するとともに、社会学的な思考方法を身につけ、自ら社会学的に思考できるようになることを目的とする。 1)ウェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』について学び、理解社会学について理解する。 2)デュルケム『自殺論』『宗教生活の原初形態』について学び、社会学主義について理解する。 3)ジンメル『貨幣の哲学』について学び、形式社会学について理解する。 |
||
| 科目名 | 現代社会論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
現代社会を「コミュニティ」の視点で捉えると、そこには個人主義化による人的関係の分断がみられる。他方、「地域資源」を活用する途を模索し、「まちづくり」という形で地域社会の再構築を促す動きがある。本講義では、地域資源をキーワードに、それを「発見し」、「磨き」、「際立たせ」、そして「発信する」という「まちづくり」に携わる地域住民の取組をみる。 1)まちづくりの現代的意義 2)地域資源とは 3)地域産業や観光資源の整備などを通した現代の地域社会の再生 |
||
| 科目名 | 社会変動論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
戦後日本社会は、高度経済成長期から、石油ショックを経て安定成長期へ、さらにバブルの崩壊を経て低成長期へと移り今日に至っている。この間に「一億総中流」と言われた社会は「無縁社会」と呼ばれる社会へと変貌した。この変化を、人口構造の変化、家族の変化、雇用の変化を通して理解することを目的とする。 1)戦後日本社会における人口構造の変化(都市化・高齢化)について学ぶ。 2)戦後日本社会における家族の変化(晩婚化・未婚化・少子化)について学ぶ。 3)戦後日本社会における雇用の変化(非正規雇用の増加)について学ぶ。 |
||
| 科目名 | 社会システム論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
システムとは要素の集合のことである。社会システム論とは社会をシステムとしてとらえる考え方である。多くの個人が集まって作られる社会では自分の思い通りにならないことが多くある。なぜ社会は思い通りにならないのかを社会システム論の概念を用いて解き明かすことを目的とする。 1)社会的行為・社会関係に関わるミクロ・レベルの概念を学ぶ。 2)集団・組織に関わるメゾ・レベルの概念を学ぶ。 3)社会構造・社会変動に関わるマクロ・レベルの概念を学ぶ。 |
||
| 科目名 | サブカルチャー論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
日本では、「サブカルチャー」を娯楽性の高いメディア文化やその消費者に対して使われる傾向にあるが、実は、国や地域、時代や集団によって指し示す意味内容が異なる多義的な概念でもある。本授業では、この「サブカルチャー」の概念について、社会学やカルチュラル・スタディーズ、メディア論やジェンダー論などの理論的知見をもとにおもに戦後日本(1950年代〜現在)の「若者文化」とそれに密接にかかわる流行を紹介し、その事象に対する分析や考察する視点を修得とする。 |
||
| 科目名 | 家族社会学A | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 3・4学期 |
| 授業の概要 |
「家族」はしばしば自明で普遍的なものとみなされることが多い。しかし、家族は時代や社会によって異なるかたちを取り、そこに紐づけられる人々の生き方も大きく変わってきた。この授業では、家族をやや長いスパンで捉え考察するとともに、現代の家族に関する社会学的な視座を獲得することを目的とする。1)近代以降の家族の変容について学び、現代にいたる過程を理解する。2)現代日本の課題である少子高齢化の構造的側面について考える。3)ジェンダーの視点を用いて家族システムや役割を捉え直す。 |
||
| 科目名 | 家族社会学B | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 3・4学期 |
| 授業の概要 |
家族は親密性の場とされる一方で、その内部に抑圧や矛盾、脆弱性を抱える場合がある。また標準とされる家族ではないことで抱える困難もある。この授業では、比較的福祉との接点が多い領域に焦点を当てて考察する。1)親密な関係性における暴力や、その構造的要因、課題について考える。2)家族の多様化、および標準からのずれがもたらす困難について学ぶ。3)現代日本の課題である高齢化、および高齢期家族の特性と課題について社会学的に考察する。 |
||
| 科目名 | 比較福祉国家論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
比較福祉国家論の研究成果をふまえて、福祉国家の歴史的展開と、近年における経済・政治・社会状況の変化に対応した福祉国家体制の再編の動きを学んでいく。1)福祉国家の国際比較の意義と比較福祉国家研究の理論の基礎を理解する。2)類型ごとの福祉国家レジームの特徴について理解を深める。3)グローバル化、情報化が進む中での新たな社会政策の国際的展開について考える。 |
||
| 科目名 | 児童虐待ソーシャルワークと子どもの権利 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 3・4学期 |
| 授業の概要 |
児童虐待対策及び児童虐待防止対策について理解し、実践力を高める。1)児童虐待対策の歴史と動向を学び、児童虐待の現状を把握し、今後の課題を検討する。2)児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律を中心として児童虐待への法的対応を学ぶ。3)児童虐待に関する知識の向上を図り、児童虐待の発生要因や背景を理解し、その課題にアプローチする。事例検討を行い、実践対応力を養う。 |
||
| 科目名 | 福祉と国連人権問題 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
国連は、人権法の包括的な機構を創設し、市民的、文化的、経済的、政治的、社会的権利など国際的に受け入れられる幅広い権利の定義を行ってきた。これらの権利を促進し、擁護し、政府がその責任を果たせるように支援する機構も作り上げてきた。国連は漸次、人権法の拡大をはかり、女性、子ども、障害者、少数者、移住労働者とその家族、難民、少数者とその他の脆弱な立場にある人々のための特定の基準を作成している。本授業では、多くの社会において差別と人権侵害に脆弱で人権を享受するには特別の保護を必要としているという認識の下に、現在の我が国の福祉政策との関連を図りながら、国際における人権問題への取扱について学ぶ。 |
||
| 科目名 | 福祉とインクルーシブ教育システム | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
インクルーシブ教育は、2006年の国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」で示されたものである。日本では、共生社会の形成に向けて、インクルーシブ教育システムの理念が重要であり、その構築のために特別支援教育を推進している。障害のある子どもが、ほかの子どもと教育を受ける権利を守るため、学校が必要な変更・調整などを行う合理的配慮を充実させることが必要である。本授業においてインクルーシブ教育の源流をたどりながら、障害者の権利条約に基づいた我が国の取り組みを考え、教育現場等における合理的配慮の実際について知り、インクルーシブ教育と特別支援教育の違いについて学ぶ。 |
||
| 科目名 | 行政学A | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 3・4学期 |
| 授業の概要 |
公共部門の中心的な主体である行政に関する基礎的な理論を理解し、今後、行政や政策に関する科目を履修していく上での基礎を習得する。具体的には以下の点について理解できるようになることを目指す。1)公共部門と市場部門の違い 2)行政の歴史と展開 3)行政における意思決定と意思決定を含む活動のプロセス 4)行政と社会、市民との関係と責任についての考え方 |
||
| 科目名 | 行政学B | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 3・4学期 |
| 授業の概要 |
日本の行政組織や制度について理解し、今後、行政や政策に関する科目を履修していく上での基礎を習得する。具体的には以下の点について理解できるようになることを目指す。 1)日本の行政組織の特徴 2)日本における国と地方自治体の行政組織の仕組み 3)日本の財政制度 4)日本の立法過程 |
||