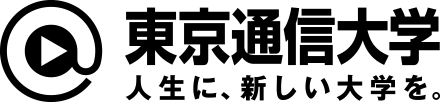専門教育科目:情報マネジメント学部
情報マネジメント学科
マネジメント
専門教育科目:情報マネジメント学部
情報マネジメント学科
マネジメント
情報マネジメント学部の専門教育科目は、情報学を実践する3つの分野と指定演習を履修します。
情報技術、システムからセキュリティ、プログラミングについて学ぶ「情報システム」、社会や組織の分析・管理・運営を学ぶ「マネジメント」、情報技術と社会の関わりやデータ分析やマーケティングを学ぶ「情報社会とデータサイエンス」、各分野をより深く理解するための「指定演習」にわかれ、総合的な「情報マネジメント」を実践します。
- <授業形態について>
-
- メディア ・・・ PCやスマートフォン等で受講できるメディア授業
- 実習 ・・・ 企業・団体で行われる実習
専門教育科目:マネジメント
※科目に関する情報は変更になる可能性があります。
マネジメント基礎
| 科目名 | 経営学入門Ⅰ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
「経営学入門Ⅰ」、「経営学入門Ⅱ」は、経営学の基礎を学ぶためのものである。経営学とは、経営に関する体系的な知識を提供する学問であり、その中心的な分析対象は、企業である。企業の経営について理解し、考える上で基礎となる概念、視点、枠組みなどを概説し、経営学をさらに広く、深く、学んでいく上での見取り図を提供する。具体的には、経営組織論、経営戦略論といった学問的な経営学の領域、あるいはマーケティング、ファイナンスといった企業活動の領域について学ぶ。「経営学入門Ⅰ」では経営学とはなにか、どのような学問なのかを理解する。 |
||
| 科目名 | 経営学入門Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
「経営学入門Ⅰ」、「経営学入門Ⅱ」は、経営学の基礎を学ぶためのものである。経営学とは、経営に関する体系的な知識を提供する学問であり、その中心的な分析対象は、企業である。企業の経営について理解し、考える上で基礎となる概念、視点、枠組みなどを概説し、経営学をさらに広く、深く、学んでいく上での見取り図を提供する。具体的には、経営組織論、経営戦略論といった学問的な経営学の領域、あるいはマーケティング、ファイナンスといった企業活動の領域について学ぶ。「経営学入門Ⅱ」ではこれまで学んだことを踏まえ、日本的経営やグローバル経営等について理解する。 |
||
| 科目名 | 簿記入門Ⅰ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
簿記とは、実務的な会計処理(お金や物の出入りの記録)であるが、企業の日々の取引から作成する貸借対照表や損益計算書の習得を目的としている。この授業では、一般的な簿記である「複式の商業簿記」を取り上げ、簿記に関する基礎的な知識を体系的に学習し、また経理の実務についても学ぶ。 1)簿記の基礎と基本について学ぶ。 2)経理の実務に関する基本を学ぶ。 3)簿記に関する基本的な専門用語を学ぶ。 |
||
| 科目名 | 簿記入門Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
この授業では、職種に関わらずビジネスにおいて、また日常において必須の経理知識と会計思考を身につけることを学ぶ。そして、基本的な商業簿記を習得し、経理関連に関わる実務的な事務処理の業務に応用できることを目指す。授業においては、商業簿記全般の必要な基本的な知識と一部、初歩的な工業簿記も学ぶが、同時にその基礎的な用語解説も随時行なっていく。なお、日商簿記3級の検定試験対策としても有用である。 1)簿記の基本について学ぶ。 2)経理の実務に関する基本を学ぶ。 3)簿記に関する専門用語を学ぶ。 |
||
| 科目名 | マーケティング概論Ⅰ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
マーケティング活動は、消費者や企業等が必要とするモノ・サービスを生産・供給することによって市場を創造する活動であり、社会に必要不可欠な活動である。本科目ではマーケティングの基本的な用語、消費者市場とビジネス市場のそれぞれの特徴、市場の細分化、ターゲット市場の決定、ポジショニングについて学ぶ。 1)マーケティングの定義と基本的な用語 2)顧客価値、顧客満足、顧客ロイヤルティ 3)消費者市場とビジネス市場の特徴 4)マーケティングのSTP(セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング) |
||
| 科目名 | マーケティング概論Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
マーケティング活動は、消費者や企業等が必要とするモノ・サービスを生産・供給することによって市場を創造する活動であり、社会に必要不可欠な活動である。この科目では「マーケティング概論Ⅰ」を学んだ学生を対象にして、マーケティング・ミックスの4つのP(製品、価格、流通経路、プロモーション)を中心にマーケティングの実践について理解する。 1)商品戦略と価格戦略 2)流通チャネルと物流マネジメント 3)マーケティング・コミュニケーション 4)広告・販売促進・広報・人的販売 5)ダイレクト・マーケティング |
||
| 科目名 | 基礎ミクロ経済学 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
現代社会に生きる人々はみな経済と密接なかかわりを持っている。本講義では、経済主体の意思決定と市場の働きを分析することが主な内容であるミクロ経済学の基本を学ぶことを第一の目的とする。この第一の目的に加え、経済学的な考え方の基本や基礎的用語の理解、わからない場合の調べ方の習得を通じ、経済情報を自分で扱えるようになることを第二の目的に、また、本講義を通じて実践的な論理的思考力を養成することを第三の目的としている。 |
||
| 科目名 | 基礎マクロ経済学 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
現代社会に生きる人々はみな経済と密接なかかわりを持っている。本講義では、現実の経済との関わりが深く、経済の全体像を正しく理解するうえで必須であるマクロ経済学の基本的な考え方を学ぶことを第一の目的とする。第二の目的は、現実に行われている様々な経済政策について自分なりに評価できるようになることである。 第三の目的としては、経済学の基本や基本的用語の理解、わからない場合の調べ方の習得を通じ、実践的な論理的思考力を養成し、かつ未知の問題に関してアプローチする方法についてもその初歩を理解することを目指す。 |
||
| 科目名 | 会計学入門Ⅰ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
「会計学入門Ⅰ」で学ぶことは、会計学の基礎である。会計学とは、経済主体(企業・政府・家計など)が行なう財産や債務、また年間の損益などに関する行為を記帳、伝達することである。つまり、会計学を学ぶことは、経済主体の財産や債務、年間の損益などを把握することができる。この授業では、その会計理論の基礎知識を体系的に学習し、また会計実務の基本についても学ぶ。 1)会計の基礎と基本について学ぶ。 2)会計実務につながる企業会計の原則を学ぶ。 3)会計に関する基本的な専門用語を学ぶ。 |
||
| 科目名 | 会計学入門Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
「会計学入門Ⅱ」で学ぶことは、会計学の応用と実践である。財務諸表の作り方と読み方を体系的に学ぶこととなる。つまり、取引の実態を知り、会計処理の手続きに関する基本的な原理・原則、思考を学ぶ。加えて財務諸表分析の技法を知り、企業評価の知識を習得することになる。 1)会計の基礎と基本をさらに理解し経済活動に会計がどのように働いているかを学ぶ。 2)会計が公表する財務諸表と各種IR情報を利用しながら企業分析ができる知識を学ぶ。 3)企業実態を理解する洞察力を学ぶ。 |
||
経営
| 科目名 | 経営管理論Ⅰ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
「経営管理論Ⅰ」および「経営管理論Ⅱ」を通じて、経営管理(マネジメント)の観点から、以下の内容を学ぶ。具体的には、テイラー、ファヨール、バーナード、チャンドラー、官僚制、人間関係論、組織構造、動機づけ、リーダーシップ、コンティンジェンシー理論、経営戦略、マーケティング、生産管理、財務管理、人的資源管理等について取り上げていく予定である。 |
||
| 科目名 | 経営管理論Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
「経営管理論Ⅰ」および「経営管理論Ⅱ」を通じて、経営管理(マネジメント)の観点から、以下の内容を学ぶ。具体的には、テイラー、ファヨール、バーナード、チャンドラー、官僚制、人間関係論、組織構造、動機づけ、リーダーシップ、コンティンジェンシー理論、経営戦略、マーケティング、生産管理、財務管理、人的資源管理等について取り上げていく予定である。 |
||
| 科目名 | 経営戦略論A | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
企業は、起業から成長、成熟を経て衰退、そして退出のサイクルを辿る。10年前にトップ企業であった企業が、今日もトップであり続けることは難しい。本科目では、日々変化する市場環境の中で、競争優位を構築するために必要な経営戦略について、理論と実践の両面を具体的な事例を通じて学ぶ 1)経営戦略の策定プロセス 2)経営戦略策定のための分析ツール 3)ポジショニング論、資源ベース論、ビジネス・ゲーム論、そのたの経営戦略論 4)ビジネスモデルとビジネスモデル分析 5)イノベーションとブルーオーシャン戦略 |
||
| 科目名 | 経営戦略論B | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
経営学の講義では事例(ケース)の分析を用いることがある。もちろん過去の事例が再現されることはないから、その事例をそっくり真似ることはできない。また、似たような状況においても、過去の経営判断が最善だとは限らない。事例を学ぶ意義は、事例から経営戦略の働き、メカニズム、経営判断に必要な基本的な論理を学ぶことにある。つまり、事例から普遍的な論理を学ぶことによって、将来直面するであろう様々な状況において正しい経営判断ができる可能性を高めることが期待できる。この科目では、多様な事例を通し、経営戦略の基本的な論理を修得することを目的としている。 |
||
| 科目名 | 経営組織論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
社会における活動は基本的にチームで行われるため、メンバーの協働をいかにして組織化していくかが経営組織のテーマである。本講義では、近代組織論、コンティンジェンシー理論、組織的知識創造などの理論を取り上げ、組織の類型や、目的に応じた組織の特徴を学ぶ。 1)社会における組織の必要性と特徴を理解する 2)様々な組織に関する理論について理解する。 3)組織と環境との関係について理解する。 |
||
| 科目名 | 組織行動論Ⅰ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
社会において、人間は個人ではなく組織として活動することが基本となる。この科目では、組織において人間がどのように行動するのか、望ましい成果を得るためにどのように行動に働きかけていくかを学ぶ。特に講義を通じて以下の点について理解を深めていく。 1)組織における人間行動の特徴とそれに働きかけることの意義を理解する。 2)組織における人間行動に影響を与える要素を理解する。 3)組織と動機づけ理論との関係について理解する。 |
||
| 科目名 | 組織行動論Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
社会において、人間は個人ではなく組織として活動することが基本となる。この科目では、人間行動に対する理解と、集団及び組織との関係について学ぶ。特に講義を通じて以下の点について理解を深めていく。 1)人間に対するものの見方について学び、それがマネジメントに与える影響について理解する。 2)集団と集団に属する人間行動との関係を理解する。 3)組織と組織に属する人間行動との関係を理解する。 |
||
| 科目名 | 情報ビジネス論Ⅰ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
コンピュータのソフトやネット上の記事や音楽、画像、動画などのデジタル・コンテンツは、容易にコピーできるだけでなく、インターネットを通じて世界中に転送できる。本科目では、具体的事例を題材にして、こうした情報財の特徴や情報財の経済原理、情報財を扱う企業の経営戦略などについて学ぶ。なお、後続科目の「情報ビジネス論Ⅱ」を続けて履修することが望ましい。 1)情報財の定義とその特徴 2)情報財の価格戦略 3)スイッチング・コストとロックイン |
||
| 科目名 | 情報ビジネス論Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
コンピュータのソフトやネット上の記事や音楽、画像、動画などの情報財は、容易にコピーできるだけでなく、インターネットを通じて世界中に転送できる。本科目では、具体的事例を題材にして、情報財特有のネットワーク効果、プラットフォーム・ビジネス、標準化問題、情報財を守る仕組みとして特許と著作権などについて学ぶ。なお、前提科目である「情報ビジネス論Ⅰ」の単位を取得してから履修すること。 1)ネットワーク効果(ネットワーク外部性) 2)プラットフォーム・ビジネスとその戦略 3)標準化戦争 |
||
| 科目名 | ベンチャー論Ⅰ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
第4次産業革命といわれるような大きな変化の中、あらゆる産業領域において新たなビジネスの創出が求められている。「ベンチャー論Ⅰ」、「ベンチャー論Ⅱ」では、ベンチャー企業の創業、大企業の新規事業の創出の際に用いるべき理論やフレームワークに関して学び、それぞれが自分のビジネスを立案できるようになることを目的とする。ベンチャー企業経営を、市場戦略、財務戦略、組織戦略の3つに分け、既存の理論、フレームワークを学ぶが、「ベンチャー論Ⅰ」では、ビジネスモデルを中心に各戦略の基本的な内容を理解する。 |
||
| 科目名 | ベンチャー論Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
第4次産業革命といわれるような大きな変化の中、あらゆる産業領域において新たなビジネスの創出が求められている。「ベンチャー論Ⅰ」、「ベンチャー論Ⅱ」では、ベンチャー企業の創業、大企業の新規事業の創出の際に用いるべき理論やフレームワークに関して学び、それぞれが自分のビジネスを立案できるようになることを目的とする。ベンチャー企業経営を、市場戦略、財務戦略、組織戦略の3つに分け、既存の理論、フレームワークを学ぶが、「ベンチャー論Ⅱ」では、「ベンチャー論Ⅰ」の内容を踏まえ、資金調達とマーケティング、組織構築に関して理解する。 |
||
| 科目名 | 人材マネジメント | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
人材マネジメントの目的は、人材を効果的・効率的に確保し、育成し、活用し、処遇し、維持することによって、組織的、個人的ならびに社会的ニーズと満足を最大限に充足することにある。この目的を達成するために、さまざまな人事施策が企画され運用されている。本科目では、特に講義を通じて以下の点について理解を深めていく。 1)人材とは何か、それをマネジメントするとはどういうことなのかを理解する。 2)人材マネジメントの目的を達成するための様々な人事施策について理解する。 3)人材マネジメントにかかわる様々な取り組みについて理解する。 |
||
| 科目名 | リーダーシップ論Ⅰ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
リーダーシップ論という科目では組織における人間行動の理解を深めることが目的となる。私たちが組織で働くとき、私たちはどのような場合にどのような反応をし、どのような行動をするのだろうか。マネジメントする側にたったとすれば、どのようにしたら働く側から望む行動を引き出せるのだろうか。講義を通じてこれらについてリーダーシップの観点から理解を深め、特に以下の点について理解を深めていく。 1)リーダーシップとは何か、なぜリーダーシップが求められるのかを知る。 2)リーダーシップに関する理論とその発展を知る。 |
||
| 科目名 | リーダーシップ論Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
リーダーシップ論という科目では組織における人間行動の理解を深めることが目的となる。私たちが組織で働くとき、私たちはどのような場合にどのような反応をし、どのような行動をするのだろうか。マネジメントする側にたったとすれば、どのようにしたら働く側から望む行動を引き出せるのだろうか。講義を通じて、これらについてリーダーシップの観点から理解を深め、特に以下の点について理解を深めていく。 1)組織における個人と集団に対するリーダーとしての働きかけに関する理論を知る。 2)社会の変遷及びそれに伴うリーダー像の変化を理解する。 |
||
| 科目名 | イノベーション論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
イノベーションとは社会に価値をもたらす革新、すなわち社会に経済的成果をもたらす革新のことである。より具体的には、製品、サービス、組織、ビジネスモデルなどに新たな考え方や技術を取り入れることで、新たな価値を生み出し、社会に経済的成果をもたらす刷新、変革をもたらすことを意味する。テクノロジーが進化する中、様々な産業分野でイノベーションを創出することが望まれている。本講義では、イノベーションの定義や分類を示したうえで、どのような誘因によってイノベーションが生まれ、普及し、進化を遂げるのか、イノベーションは企業活動にどのような影響を及ぼすのか、そして、その普及や進化の過程にはどのようなプレイヤーが関与しているのかを学ぶ。 |
||
経済・商学・会計
| 科目名 | 管理会計論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
企業会計は、企業外部の利害関係者に加え、企業内部の利害関係者にも会計情報(経営管理に役立つ会計情報)を提供する必要がある。そのための会計が「管理会計」と言われる学問である。つまり、管理会計とは、企業内部の経営管理者に有用な情報を必要に応じて作成し、報告する会計である。この授業では、企業経営(management)に役立つ内部会計(accounting)の基本を学習する。 企業内部の経営管理者に有用な情報を作成、報告する会計について学ぶ。 1)企業会計としての管理会計とは何かについて学ぶ。 2)企業経営(management)に役立つ内部会計(accounting)の基本を学ぶ。 3)管理会計に関する専門用語を学ぶ。 |
||
| 科目名 | 金融論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
金融という言葉は「お金を融通すること」を意味する。もう少し細かく言えば、「経済の中で、当面資金に余裕がある人から当面資金を必要とする人にお金を融通すること」である。本講義は経済学の入門的知識を前提に、マクロ金融とミクロ金融(=ファイナンス)の双方について学習する。金利やリスクなど金融あるいはファイナンスの基本事項からはじめ、経済全体における金融の意義と役割などについて考えていくこととする。なお経済学の基礎的知識については本講義でも復習する。 |
||
| 科目名 | ゲーム理論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
この講義では『ゲーム理論』の基本的な考え方を学ぶ。 現在、ゲーム理論は経済学、政治学、社会学、生物学、心理学等々に幅広く利用されている。従ってゲーム理論は、こうした分野の基礎的ツールとして、また、 複数の意思決定主体が、意思決定の際に相互に依存しあう状況を分析するツールとしての意味を持っている。ゲーム理論を学ぶことで、自分自身の意志決定においてもその考え方を役立てることができるようになっていただきたい。なおゲーム理論自体は「応用数学」に属するが、本講義では四則演算と簡単な確率の概念がわかっていればよい。 |
||
| 科目名 | 財政学 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
財政とは端的には政府部門の(経済)活動あるいはその集積の結果である。この講義では、通常議論の前提となっている「そもそも政府部門あるいは公的セクターが、なぜ一国経済の中で必要となるのか」というところから議論を始める。そして、政府部門の果たすべき役割を議論していく中で、政府の支出と収入についても考える。一方で財政は制度的な要因によっても大きく左右される。そこで、現実の財政制度とその構造についても批判的に検討を行うこととする。 |
||
| 科目名 | ビジネス経済学 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
本講義を一言で表現すれば、ビジネスに役立つ経済学の講義である。ビジネスに役立つということは、言い換えれば経営上の課題について解決を図るということであり、経営上の課題について主にミクロ経済学の応用という立場から考えていくのが本講義である。時間も限られているため、経営上の課題とそれを取り巻くトピックスについては絞り込む必要がある。本講義では、特に、市場構造、市場支配力、費用の問題、交渉力と情報に重点を置いて解説していく。なお、基礎ミクロ経済学の知識だけでは足りない部分についても講義の中で補うこととする。 |
||
| 科目名 | 広告論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
パブリック・リレイションズ(PR)は、広告と訳される。日本の広告とメディアの現状、広告理論としてのステレオタイプ理論と、パラダイムシフト理論を教える。広告効果はあるのか。新聞広告と雑誌などの活字メディアの広告が、主流であった。テレビの普及とインターネット・メディアの拡大で、新聞広告の減少が激しい。パブリック・リレイションズ(PR)は、広報とも訳される。広報の役割と意義について学ぶ、広報は日本ではまだ十分に理解されていない。報道官の役割についても教える。 |
||
| 科目名 | 消費者行動論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
消費者行動は、経済学、心理学、社会学をはじめマーケティング等様々な分野の研究対象となってきた。そのため消費者行動研究は、こうした幅広い学問分野の理論を援用する形で発展してきた。その結果、単一の学問領域の知識だけで捉えきれない消費者の行動を、幅広い視野から説明することを可能にした反面、理論を統一化し一般化していくという流れの形成にはあまり成功しなかったようである。本講義では、経済学の視点から消費者行動理論・研究を整理し直し、提示することで今後の消費行動研究の礎を提供することを目標としている。 |
||
| 科目名 | 財務会計論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
財務会計論は、将来企業の経理業務につく人ばかりでなく、多くの学生に生活を賢く生きるためには必要な科目になっています。会計の知識だけではなく、本を読む力やプレゼンテーション能力も向上させられるように意識して進めます。 1)日商簿記検定3級やビジネス会計検定3級を目指す基本的知識を理解する。 2)財務会計関連の雑誌論文の輪読および文献の検索ができるようになる。 3)有価証券報告書を用いての財務分析の基本的な側面を理解する。 |
||