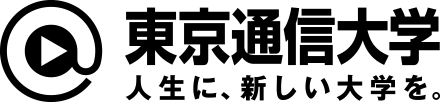専門教育科目:人間福祉学部
人間福祉学科
精神保健福祉
専門教育科目:人間福祉学部
人間福祉学科
精神保健福祉
人間福祉学部の専門教育科目は、6つの分野を総合的に学びます。医学、心理学、社会保障などを学ぶ「ソーシャルワーク」、様々な支援の取り組みや体制について学ぶ「包括的支援体制の基礎」、人間の生活を支える福祉を体系的に学ぶ「社会福祉」と「精神保健福祉」、人間の個別性と多様性を理解するための「総合人間」、実地の演習を通じて各分野に対する実践力を身につける「フィールドスタディ」。これらの科目を学ぶことで、従来の専門的福祉教育に加え、人間社会に対する広範な知識を身につけます。
※3年次編入学の方へ
厚生労働省による社会福祉・精神保健福祉養成課程のカリキュラム見直しにより、一部科目の科目名、単位数、標準履修年次などが異なります。
3年次編入学の指定科目名称は「国家資格取得に関する案内」で確認ください。
- <授業形態について>
-
- メディア ・・・ PCやスマートフォン等で受講できるメディア授業
- スクーリング ・・・ スクーリング会場で行われる授業
- 実習 ・・・ 福祉施設・機関で行われる実習
専門教育科目:精神保健福祉
※科目に関する情報は変更になる可能性があります。
精神保健福祉の知識
| 科目名 | ソーシャルワークの理論と方法(精神専門)A | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 2 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
精神科ソーシャルワーカー(以下、PSW)は、精神障害者の「社会的復権・権利擁護と福祉」のために専門的・社会的活動を行う専門職である。この授業では、対象者となる人々が多様化し、自然環境の変化に伴い社会が変化していく中で、その目的を達成するために用いるソーシャル・ケースワークに関する基礎的かつ専門的な知識と、実践場面における実際的な技術を習得することを目指す。具体的には、以下の内容を取り上げ、学んでいくこととする。具体的には以下の項目を学ぶ。 1)精神保健福祉分野のソーシャルワークの概要 2)精神保健福祉分野のソーシャルワークの過程 3)精神保健福祉分野における家族支援の実際 4)多職種連携・多機関連携(チームアプローチ) |
||
| 科目名 | ソーシャルワークの理論と方法(精神専門)B | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 2 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
精神科ソーシャルワーカー(以下、PSW)は、精神障害者の「社会的復権・権利擁護と福祉」のために専門的・社会的活動を行う専門職である。この授業では、その目的を達成するために用いるソーシャル・ケースワークに関する基礎的かつ専門的な知識と、実践場面における実際的な技術を習得することを目指す。具体的には、以下の内容を取り上げ、学んでいくこととする。 1)ソーシャルアドミニストレーションの展開方法 2)コミュニティワーク 3)個別支援からソーシャルアクションへの展開 4)関連分野における精神保健福祉士の実践展開 |
||
| 科目名 | 精神医学と精神医療A | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 2 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
精神保健福祉領域における福祉援助者として従事する際に、医療関係者との連携が絶対不可欠となる。精神障害者に対しての支援を実施する際にも精神医療における基本的な知識は求められる。本授業においては精神医療に関する基礎的・基本的な事柄を学習することとする。 1)精神医療における基本的事柄(歴史、生物学的基礎)を学習する。 2)精神障害の概念と精神疾患の分類を考察する。 3)精神疾患の症状と診断について理解する。 |
||
| 科目名 | 精神医学と精神医療B | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 2 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
精神保健福祉領域における福祉援助者として従事する際に、医療関係者との連携が絶対不可欠となる。また、精神障害者に対しての支援を実施する際にも精神医療における基本的な知識は求められる。本授業においては精神医療のなかでも精神疾患の治療と、精神科医療機関の治療構造・専門病棟について学習することとする。 1)精神科薬物療法・電気けいれん療法等の身体療法について学ぶ。 2)精神療法、精神科リハビリテーションの内容について学ぶ。 3)精神科の受診状況や外来・入院・在宅医療等について学ぶ。 |
||
| 科目名 | 精神保健福祉の原理A | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 2 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
1)障害者福祉の思想と原理、障害者福祉の理念、障害者福祉の歴史的展開を学ぶ。 2)精神保健福祉士が対象とする「精神障害者」の定義とその障害特性とともに、精神障害者の生活実態について学ぶ。 3)諸外国の動向、日本の精神保健福祉施策に影響を与えた出来事、わが国の最近の動向、わが国の課題と社会的障壁について学ぶ。 |
||
| 科目名 | 精神保健福祉の原理B | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 2 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
「精神保健福祉の原理A」を受けて、本授業では、精神障害者を取り巻く生活実態について把握した上で、「精神保健福祉士」としてソーシャルワーク実践を展開していくために、「精神保健福祉士」の資格化に至る歴史を概観し、精神保健福祉の原理と理念を確認したうえで、「精神保健福祉士」の機能と役割について学ぶ。 1)「精神保健福祉士」の資格化の経緯を把握し、精神保健福祉の原理と理念について、確認する。 2)「精神保健福祉士法」「精神保健福祉士の倫理綱領」の意義と内容について、把握する。 3)「精神保健福祉士業務指針」の概要を把握し、精神保健福祉士の業務特性、機能と役割について説明できるようになる。 |
||
| 科目名 | 精神障害リハビリテーション論A | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
本授業では、精神保健福祉士として精神障害リハビリテーションを実践で活用するために、精神障害リハビリテーションの基盤となる概要と、その構成と展開について学ぶ。 1)精神障害リハビリテーションの理念、定義、基本原則について、把握する。 2)精神障害リハビリテーションの構成及び展開について、理解する。 3)精神障害リハビリテーションとソーシャルワークの関係について学ぶ。 |
||
| 科目名 | 精神障害リハビリテーション論B | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
「精神障害リハビリテーション論A」を受けて、本授業では、精神障害リハビリテーションプログラムを実践で活用するために、具体的なリハビリテーションプログラム内容と実施機関について把握するとともに、精神障害リハビリテーションの動向と実際について学ぶ。 1)精神障害リハビリテーションプログラムの具体的な内容について、理解する。 2)精神障害リハビリテーションプログラムの実施機関について、把握する。 3)精神障害リハビリテーションの近年の動向と実際について学ぶ。 |
||
| 科目名 | 精神保健福祉制度論 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 2 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
本授業では、精神障害者及びメンタルヘルスの課題を抱える人に対して、状況に応じて適切な法制度の活用を支援するために、精神障害者に関する各種法制度についての概要と課題について理解し、法制度における精神保健福祉士の役割について学ぶ。 1)精神障害者の医療に関する制度について理解する。 2)精神障害者の生活支援に関する制度について理解する。 3)精神障害者の経済的支援に関する制度について理解する。 |
||
| 科目名 | 現代の精神保健の課題と支援A | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 2 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
本授業では、現代社会における多様なメンタルヘルスの課題に対応するために、精神保健の概要および現代の精神保健分野の動向と基本的考え方を理解したうえで、家族に関連する精神保健の課題と支援、精神保健の視点から見た学校教育の課題とアプローチについて学ぶ。 1)精神保健の概要を理解し、現代における精神保健分野の動向と基本的考え方について把握する。 2)家庭および学校教育における精神保健の課題およびその支援について理解する。 3)多種多様な現代社会の課題について、メンタルヘルスの視点からの把握とアプローチについて学ぶ。 |
||
| 科目名 | 現代の精神保健の課題と支援B | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 2 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
「精神保健の課題と支援A」を受けて、本授業では、精神保健の視点から見た勤労者の課題、地域精神保健活動とその課題、精神保健の視点から見た現代社会の課題、精神保健福祉対策と精神保健福祉士の役割、精神保健関連機関の役割と連携、諸外国の精神保健活動の現状および対策について学んでいく。 1)勤労者の精神保健問題や、職場の精神保健に対する対策を理解する。 2)現代社会の精神保健の課題とアプローチを確認する。 3)精神障害者、認知症、アルコール関連問題、薬物乱用防止、ギャンブル依存へのアプローチを学ぶ。 |
||
精神保健福祉の技術
| 科目名 | ソーシャルワーク演習(精神専門)A | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 2 | 授業形態 | メディア・面接 |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 3~4学期 |
| 授業の概要 |
1)精神保健福祉士として身につけなければならない基本的な技術、知識の応用力、価値や倫理判断を修得する。 2)利用者及び他職種とのチームケアでの構えや対応を実践的に学ぶ。 3)地域での支援展開を具体的な実践場面を想定したロールプレイ等で学ぶ。 |
||
| 科目名 | ソーシャルワーク演習(精神専門)B | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 2 | 授業形態 | メディア・面接 |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 3~4学期 |
| 授業の概要 |
「ソーシャルワーク演習」で体験的に学んだことをもとに、精神障害者への支援で用いる援助技術について、実践的理解が深まるような演習を行う。 1)精神保健福祉士の演習の意義と目的を理解する。 2)ソーシャルワークの課題;個人(受診援助から退院支援)・グループ(デイケア、地域の障害福祉サービス)・地域社会(地域福祉の基盤整備にかかわる相談援助)を通じた演習を行う。 3)精神障害リハビリテーションの主な技術(心理教育、デイケア、SST、就労支援など)の修得につながる演習を行う。 4)支援の場に応じた相談援助の理解(精神科医療機関、障害福祉サービス事業所、市町村・保健所・精神保健福祉センターなどの行政機関、教育機関、社会福祉協議会、地域包括支援センター、ハローワーク、司法機関、産業など) |
||
| 科目名 | ソーシャルワーク演習(精神専門)C | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 2 | 授業形態 | メディア・面接 |
| 標準履修年次 | 4年次 | 開講期 | 1~2学期 |
| 授業の概要 |
精神保健福祉士が支援を展開する具体的な現場における事例を中心に、実習前及び実習後を含んで、実践的に修得する。特に、精神保健福祉士が身に着けるべき価値、知識及び技術について実践的な修得をめざせるようにする。 |
||
| 科目名 | ソーシャルワーク実習指導(精神専門)A | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 2 | 授業形態 | メディア・面接 |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 1~2学期 |
| 授業の概要 |
精神保健福祉領域におけるソーシャルワークの実践においては、専門的知識と技術の習得が求められる。技術の習得では、理論的な講義もさることながら、「ソーシャルワーク実習(精神専門)」で学ぶことが多い。そのため、本授業は、現場実習に向けて事前学習として位置づけられている科目である。実習に必要な下記の内容について学習する。 1)ソーシャルワーク実習(精神専門)の意義について 2)精神障害者の置かれている現状・生活上の困難について 3)実習を行う地域資源及び実習施設等の情報収集について |
||
| 科目名 | ソーシャルワーク実習指導(精神専門)B | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 2 | 授業形態 | メディア・面接 |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 3~4学期 |
| 授業の概要 |
精神保健福祉領域におけるソーシャルワークの実践においては、専門的知識と技術の習得が求められる。技術の習得では、理論的な講義もさることながら、「ソーシャルワーク実習(精神専門)」で学ぶことが多い。そのため、本授業は、現場実習に向けて事前学習として位置づけられている科目である。実習に必要な下記の内容について学習する。 1)ソーシャルワーク実習(精神専門)の意義について 2)精神障害者の置かれている現状・生活上の困難について 3)実習を行う地域資源及び実習施設等の情報収集について |
||
| 科目名 | ソーシャルワーク実習指導(精神専門)C | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 2 | 授業形態 | メディア・面接 |
| 標準履修年次 | 4年次 | 開講期 | 1~2学期 |
| 授業の概要 |
実習体験を振り返り、実習現場における自らの態度や行動を自己点検することで、対人援助職としての自己理解を深めることができる。授業で深めた内容は実習総括レポートとしてまとめ、面接授業で実施する実習報告会で発表する。そのことを通して、自分自身を内省し体験の概念化をする。 1)実習現場・内容について振り返りと情報の共有を図る。 2)実習総括レポートを作成する。 3)実習報告会(実習の評価全体総括会)を実施する。 |
||
| 科目名 | ソーシャルワーク実習(精神専門)A | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 2 | 授業形態 | 面接 |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 4学期 |
| 授業の概要 |
実習を通じて、専門職者としての求められる態度を学び、また、サービス中における自己の専門職者としての態度について客観的に洞察をする。 1)それまでに学習した専門的な理論や援助技術等の知識と実際の活動との結びつきを意識して各自がテーマを設定し、積極的に実習を行う。 2)精神科病院もしくは精神科診療所にて実習を行う。 3)利用者の理解と援助の実際について考察し、実習日誌にまとめる。 精神科医療機関で12日間以上の現場実習を行い、ソーシャルワーク実習(精神専門)担当教員が、週1回、実習先への巡回指導または帰校指導を行う。 |
||
| 科目名 | ソーシャルワーク実習(精神専門)B | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 2 | 授業形態 | 面接 |
| 標準履修年次 | 4年次 | 開講期 | 1学期 |
| 授業の概要 |
実習を通じて専門職者として求められる態度を学び、また、サービス中における自己の専門職者としての態度について客観的に洞察をする。 1)それまでに学習した専門的な理論や援助技術等の知識と実際の活動との結びつきを意識して各自がテーマを設定し、積極的に実習を行う。 2)地域の障害福祉サービス事業を行う施設等にて実習を行う。 3)利用者の理解と援助の実際について考察し、実習日誌にまとめる。 精神障害者福祉施設・機関で16日間以上の現場実習を行い、ソーシャルワーク実習担当教員が、週1回、実習先への巡回指導または帰校指導を行う。 |
||