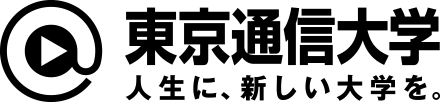専門教育科目:人間福祉学部
人間福祉学科
社会福祉
専門教育科目:人間福祉学部
人間福祉学科
社会福祉
人間福祉学部の専門教育科目は、6つの分野を総合的に学びます。医学、心理学、社会保障などを学ぶ「ソーシャルワーク」、様々な支援の取り組みや体制について学ぶ「包括的支援体制の基礎」、人間の生活を支える福祉を体系的に学ぶ「社会福祉」と「精神保健福祉」、人間の個別性と多様性を理解するための「総合人間」、実地の演習を通じて各分野に対する実践力を身につける「フィールドスタディ」。これらの科目を学ぶことで、従来の専門的福祉教育に加え、人間社会に対する広範な知識を身につけます。
※3年次編入学の方へ
厚生労働省による社会福祉・精神保健福祉養成課程のカリキュラム見直しにより、一部科目の科目名、単位数、標準履修年次などが異なります。
3年次編入学の指定科目名称は「国家資格取得に関する案内」で確認ください。
- <授業形態について>
-
- メディア ・・・ PCやスマートフォン等で受講できるメディア授業
- スクーリング ・・・ スクーリング会場で行われる授業
- 実習 ・・・ 福祉施設・機関で行われる実習
専門教育科目:社会福祉
※科目に関する情報は変更になる可能性があります。
社会福祉の知識
| 科目名 | 高齢者福祉A | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
人口構造の少子高齢化や家族形態の変化などにより、高齢者を支える社会の仕組みは変容を迫られてきた。この授業では、人口や世帯構造の変化とともに、加齢に伴う心身の変化や、高齢者を取り巻く環境について理解したうえで、現行の高齢者福祉の体制について学んでいく。 1)高齢者を取り巻く環境の変化について学ぶ。 2)高齢期の心身の状況について学ぶ。 3)認知症施策や介護保険制度などについて学ぶ。 |
||
| 科目名 | 高齢者福祉B | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
人口構造の少子高齢化や家族形態の変化などにより、高齢者を支える社会の仕組みは変容を迫られてきた。この授業では、介護保険制度の現状や制度改正の背景と経緯、その他の高齢者福祉の体制について学んでいく。 1)介護保険制度について学ぶ。 2)介護保険制度以外の、高齢者を支える制度について学ぶ。 |
||
| 科目名 | 児童・家庭福祉A | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
子どもの成長・発達の特性を踏まえ、子ども家庭福祉の理念と意義について理解する。子どもが持つ成長・発達の特性および権利について学習し、その時々に合致した、子ども家庭福祉のニーズを把握する。全ての児童が児童福祉の対象であること、児童福祉法をはじめとする関連法に基づいた制度の理解、および少子化に伴う子育て支援の現状や必要性を理解する。 |
||
| 科目名 | 児童・家庭福祉B | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 1年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
子どものおかれた現状と子どもとその家庭をめぐる福祉的課題を理解し、児童福祉の理念・意義、サービス、援助方法についての学びを深める。さらに、具体的な問題をソーシャルワークの視点からとらえ、ソーシャルワーカーとして援助実践方法を事例を通して学ぶ。 |
||
| 科目名 | 福祉サービスの組織と経営A | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
本講義では、ソーシャルワークにおいて必要となる、福祉サービスについてその特徴を利用者、事業者の立場から理解する。併せて、サービスを提供する組織とその経営管理について基礎的な知識を身につけることを学ぶ。 1)福祉サービスに係る組織や団体(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、営利法人、市民団体、自治会など)について学ぶ。 2)福祉サービスの組織と経営に係る基礎理論および労働者の権利等について学ぶ。 3)経営戦略の基礎概念、集団力学・リーダーシップに関する基礎理論について理解する。 |
||
| 科目名 | 福祉サービスの組織と経営B | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
本講義では、「福祉サービスの組織と経営A」で学ぶ、ソーシャルワークにおいて必要となる、福祉サービスについてその特徴を利用者、事業者の立場から理解し、サービスを提供する組織とその経営管理についての基礎的な知識を基に、実際の福祉サービスの管理運営の方法について理解を深める。 1)福祉サービスのサービス管理について学ぶ。 2)福祉サービスの人事管理と労務管理について学ぶ。 3)福祉サービスの会計管理と財務管理について学ぶ。 4)福祉サービスの情報管理と福祉人材マネジメントについて学ぶ。 |
||
| 科目名 | ソーシャルワークの基盤と専門職(社会専門) | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 2 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
「ソーシャルワークの基盤と専門職」では、社会福祉の原理・原則や制度を基盤とし、社会福祉援助活動の意義、目的と原則及び過程を理解した上で、ソーシャルワークの基本概念、人権尊重、社会正義等ソーシャルワークが寄って立つ理念についても学習した。この授業では、さらに以下の内容を取り上げて学ぶこととする。 1)ソーシャルワークに係る専門職の概念と範囲 2)ミクロ・メゾ・マクロレベルにおけるソーシャルワーク 3)総合的かつ包括的な支援支援と多職種連携の意義と内容 |
||
| 科目名 | ソーシャルワークの理論と方法(社会専門)A | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 2 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
「ソーシャルワークの理論と方法A・B」の学びをふまえ、社会福祉士に必要な知識・技術を身につけることに留意していく。授業の目標達成のために以下の4点を中心に取り上げ、授業を展開していく。 1)ソーシャルワークにおける援助関係の形成 2)ソーシャルワークにおける社会資源の活用・調整・開発 3)ネットワークの形成 4)ソーシャルワークに関連する方法等 |
||
| 科目名 | ソーシャルワークの理論と方法(社会専門)B | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 2 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
「ソーシャルワークの理論と方法(社会専門)A」の学びに続き、社会福祉士に必要な知識・技術を身につけることに留意していく。授業の目標達成のために以下の3点を中心に取り上げ、授業を展開していく。 1)カンファレンス 2)事例分析 3)ソーシャルワークにおける総合的かつ包括的な支援の実際 |
||
| 科目名 | 保健医療と福祉A | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
本講義の目的は、相談援助活動において必要となる医療保険制度や保健医療サービスの基礎的知識について理解することである。具体的には、次のとおりの課題を理解する。 1)保健医療サービスを提供する施設とシステムについて、医療法、診療報酬、介護保険法と関連づけて理解する。 2)保健医療サービス提供と経済的保障として、診療報酬、介護報酬、公費負担医療制度について理解する。 |
||
| 科目名 | 保健医療と福祉B | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
本講義の目的は、保健医療サービスにおける専門職の役割と実際、多職種協働について理解することである。具体的には、次のとおりの課題を理解する。 1)保健医療サービスと社会福祉専門職の役割について理解する。 2)保健医療サービスにおける医療ソーシャルワーカーなど専門職の役割とチームケア実現のための基礎知識について理解する。 3)地域における保健医療ネットワークの制度と実際について理解する。 |
||
| 科目名 | 公的扶助論A | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 1・3学期 |
| 授業の概要 |
欧米や日本における公的扶助の概念や、その前史を含めた歴史的経緯について確認する。さらに生活保護制度の目的や仕組み、関係する各種サービス内容について、基本的かつ具体的な内容について学んでいくこととする。 1)公的扶助の概念や貧困問題の取り上げ方、対処方法等について学ぶ。 2)ヨーロッパや日本における公的扶助制度の歴史や発展過程について学ぶ。 3)日本の生活保護制度の目的や原理、原則、具体的な仕組み等について学ぶ。 |
||
| 科目名 | 公的扶助論B | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1 | 授業形態 | メディア |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 2・4学期 |
| 授業の概要 |
「公的扶助論A」で学んだ公的扶助、生活保護制度に関する概念や基本的な知識、サービス内容をもとに、本授業では、生活保護制度の具体的な運用方法や動向の現状、生活困窮者自立支援制度や生活福祉資金といった低所得者対策等についても学ぶこととする。 1)生活保護制度の昨今の動向や関連する行政機関等について学ぶ。 2)生活困窮者自立支援制度や生活福祉資金等、他の低所得者対策について学ぶ。 3)生活保護制度などにおける相談援助活動について学ぶ。 |
||
社会福祉の技術
| 科目名 | ソーシャルワーク演習(社会専門)A | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 4 | 授業形態 | メディア・面接 |
| 標準履修年次 | 2年次 | 開講期 | 3~4学期 |
| 授業の概要 |
社会福祉士が専門的業務を展開する上で必要とされる基本的な知識・技術・価値等について、事例を通して学ぶ。ソーシャルワークの展開過程と社会福祉士の活動を結びつけて理解し、ミクロ、メゾ、マクロレベルのソーシャルワークの統合的実践を意識して学ぶ。 1)ソーシャルワークの展開過程と社会福祉士の活動を結びつけて学ぶ。 2)支援を必要とする人を中心とした分野横断的な総合的かつ包括的な支援のために必要な知識・技術・価値等について実践的に学ぶ。 3)ミクロ、メゾ、マクロレベルのソーシャルワークの統合的実践を学ぶ。 |
||
| 科目名 | ソーシャルワーク演習(社会専門)B | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 4 | 授業形態 | メディア・面接 |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 3~2学期 |
| 授業の概要 |
メディア授業・面接授業とも、1グループ学生20名以内に割り振り、担当教員の10名で各グループを担当する。以下の4点を中心に進めていく。 1)地域の特性や課題を把握し解決するための、地域アセスメントや評価等の仕組みを実践的に学ぶ。 2)ミクロ・メゾ・マクロレベルにおけるソーシャルワークの対象と展開過程、実践モデルとアプローチについて実践的に学ぶ。 3)実習を通じて体験した事例について、事例検討や事例研究を実際に行い、その意義や方法を具体的に学ぶ。 4)実践の質の向上を図るため、スーパービジョンについて体験的に学ぶ。 |
||
| 科目名 | ソーシャルワーク実習指導(社会専門)A | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 3 | 授業形態 | メディア・面接 |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 1~2学期 |
| 授業の概要 |
ソーシャルワーク実習は、高齢者、障害者、児童、地域、行政など様々な分野や種別に配属され、実習が行われる。そのため、ソーシャルワーク実習指導では、単に「職場体験」や「特定施設での援助体験」をすることではなく、普遍的なソーシャルワーク技術を学び体得することを目指す。その事前準備に取り組むこととなる。 1)ソーシャルワーク実習とソーシャルワーク実習指導における個別指導及び集団指導の意義について理解する。 2)ソーシャルワーク実習の意味・必要性・基本的態度について理解する。 3)様々な実習施設・機関の役割・機能、職員体制等をそれぞれ調べる。 4)ソーシャルワークに即した実習計画(実習生、実習担当教員、実習先の実習指導者との三者協議を踏まえた)を立案し、作成する。 |
||
| 科目名 | ソーシャルワーク実習指導(社会専門)B | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 3 | 授業形態 | メディア・面接 |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 3~2学期 |
| 授業の概要 |
「ソーシャルワーク実習指導(社会専門)B」では、事前指導に加え、高齢者、障害者、児童、地域、行政など様々な分野や種別に配属された後に、事後指導として行われる。実習での振り返りを中心に、利用者や現場職員と接した体験をもとに、相談援助のあり方について確認していく。また、振り返りの一環として実習総括レポートの作成や報告等も行う。 1)各自が実習先の施設・機関の紹介、実習内容等の報告を行う。 2)実習総括レポートの作成を行う。 3)実習先からの評価表をもとに、相談援助実習に対する自己評価を行う。 |
||
| 科目名 | ソーシャルワーク実習(社会専門) | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 6 | 授業形態 | 面接 |
| 標準履修年次 | 3年次 | 開講期 | 4~1学期 |
| 授業の概要 |
ソーシャルワーク実習は、様々な分野や種別に配属され、32日以上、240時間以上取り組むこととなる。それは単に「職場体験」や「特定施設での援助体験」をするだけではなく、個別の場での体験を通じながらも、援助実践現場に出ても対応できる通底的・普遍的なソーシャルワーク技術を学び体得することである。 1)あらゆる相談援助場面でどのようにソーシャルワークが展開されるのか理解する。 2)「ミクロ」「メゾ」「マクロ」ソーシャルワークに関する体験を理解する。 3)「個人アセスメント体験」と「地域アセスメント体験」を理解する。 1グループ学生20名以内に割り振り、グループ指導を担当する。 社会福祉施設・機関で32日間以上の現場実習を行い、ソーシャルワーク実習担当教員が、週1回、実習先への巡回指導または帰校指導を行う。 |
||